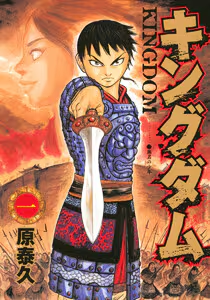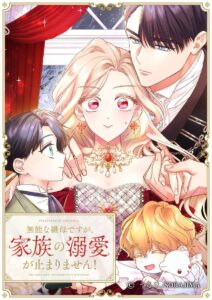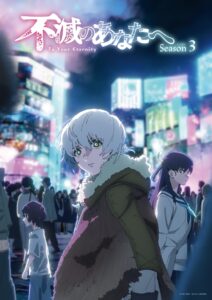「楊端和って実際は男性だったって本当?」「山の民って史実に存在したの?」「キングダムのどこまでが史実で、どこからが創作なの?」
キングダムを読んでいて、こんな疑問を抱いたことはありませんか?美しく強い山の民の女王・楊端和に魅了されながらも、「実際の歴史ではどうだったんだろう?」と気になってしまう方は多いはずです。
実は、楊端和は史実に実在した男性将軍でした。そして山の民という集団は、完全にキングダムオリジナルの創作設定だったのです。
この記事を読むことで、以下のことが分かります:
史実を知ることで、キングダムの創作の巧みさがより一層際立って見えてきます。歴史の真実を理解した上で作品を楽しめば、今まで以上にキングダムの世界に没入できることでしょう。
それでは、楊端和と山の民の本当の姿を一緒に探っていきましょう。

▼キングダム【期間限定無料】
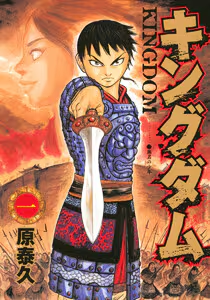
楊端和の史実と男性説の真実|実在した秦の将軍の正体

楊端和は史実に確実に実在した男性将軍でした。中国最古の歴史書『史記』に9年間の活動記録が残されており、秦の中華統一事業において重要な役割を果たしていたのです。キングダムの美しい女王という設定は、原作者による見事な創作アレンジです。
史実の楊端和は確実に実在した人物
楊端和という人物は、間違いなく史実に実在していました。中国最古の歴史書『史記』の「秦始皇本紀」に、その活動が明確に記録されているからです。
『史記』秦始皇本紀での記録
司馬遷が編纂した『史記』では、楊端和について以下のように記載されています:
- 「九年,楊端和攻衍氏」(9年、楊端和が衍氏を攻めた)
- 「十一年,王翦、桓齮、楊端和攻鄴,取九城」(11年、王翦・桓齮・楊端和が鄴を攻め、9城を取った)
- 「十八年,端和囲邯鄲城」(18年、端和が邯鄲城を囲んだ)
これらの記録は、楊端和が秦王政(後の始皇帝)の重要な軍事作戦に参加していたことを示しています。史記は中国史学の基本資料であり、その記述の信頼性は極めて高いといえるでしょう。
活動期間は9年間のみ
興味深いことに、史実の楊端和の活動記録は、わずか9年間(紀元前238年~229年)しかありません。この短期間に3つの重要な戦果を挙げていることから、楊端和がいかに優秀な将軍だったかが分かります。
活動期間の短さは、逆に楊端和の実力の高さを物語っているのです。短期間で秦の中華統一事業の要となる作戦に次々と参加できたということは、始皇帝からの信頼が厚かったことの証拠といえます。
王翦・桓齮との共闘記録
楊端和は、秦軍最高司令官クラスの将軍たちと肩を並べて戦った記録があります。特に紀元前236年の鄴攻めでは、王翦・桓齮という錚々たる名将と共に作戦を遂行しました。
王翦は後に楚を滅ぼす大功を立て、桓齮は趙の名将・李牧と激闘を繰り広げた猛将です。そんな一流の将軍たちと対等に作戦に参加できたということは、楊端和の軍事的才能が相当なものだったことを示しています。
楊端和が男性だった決定的証拠
史実の楊端和は、間違いなく男性でした。この点について、複数の角度から証拠をご紹介いたします。
古代中国で女性将軍は記録される
古代中国において、女性が将軍として活躍することは極めて稀でした。もし楊端和が女性だったなら、それは非常に特異なケースとして史書に詳しく記録されたはずです。
実際に、中国史上で女性将軍として活躍した人物(例:花木蘭など)は、その性別について明確に記載されています。しかし楊端和については、そのような記述が一切ないのです。
史書の記録方法を考えると、性別について特記されていないということは、楊端和が一般的な男性将軍だったことを意味しています。
史書に性別記載がない理由
史記などの史書では、将軍の性別について特に言及しないのが通常でした。なぜなら、将軍はほぼ例外なく男性だったからです。
女性が将軍となるケースは極めて特殊で、そのような場合には必ず「女将軍」「女性である」といった記述が加えられました。楊端和にそのような記載がないということは、楊端和が男性だったことの決定的な証拠といえるでしょう。
キングダムで女性に変更された背景
実は、キングダムの楊端和も当初は男性として設定されていました。公式ガイドブック「英傑列記」でこの事実が明らかになっています。
女性に変更された理由として考えられるのは:
- 物語に華を添えるため
- 戦国時代の武将は男性ばかりで、作品に多様性を持たせる必要があった
- 史実での記録が少ない人物だからこそ、大胆な創作が可能だった
原泰久先生の見事な創作により、史実の男性将軍が魅力的な女性キャラクターに生まれ変わったのです。
史実の楊端和の戦歴と功績
楊端和の史実での活躍は、秦の中華統一事業において重要な役割を果たしました。その戦歴を時系列でご紹介いたします。
紀元前238年:魏の衍氏攻略
楊端和が史書に初めて登場するのが、この魏の衍氏攻略戦です。この年は秦国内で嫪毐の乱や成蟜の反乱が起きるなど、政情が不安定な時期でした。
しかし、そんな混乱の中でも楊端和は確実に対外作戦を成功させています。国内が政治的混乱に陥っていた時期に重要な軍事作戦を任されたということは、楊端和への信頼がいかに厚かったかを物語っています。
衍氏の攻略は、魏の勢力を削ぐ重要な作戦でした。この成功により、楊端和は秦王政から高く評価されることになったのです。
紀元前236年:趙の鄴攻め
この戦いこそ、楊端和の実力を示す最も重要な作戦でした。王翦・桓齮・楊端和の三将が連携して趙の重要拠点・鄴を攻撃し、なんと9つもの城を陥落させる大戦果を挙げたのです。
鄴は趙の重要拠点であり、その攻略は趙滅亡への重要な一歩でした。この作戦の成功により、秦の中華統一事業は大きく前進することになります。
楊端和が名将・王翦と桓齮と共に名を連ねているということは、彼の軍事的才能が最高レベルにあったことを示しています。
紀元前229年:邯鄲包囲の重責
楊端和最後の記録となるのが、趙の首都・邯鄲包囲戦です。楊端和は河内の兵を率いて邯鄲を包囲するという、まさに趙滅亡の最終段階を担う重責を任されました。
邯鄲は趙の首都であり、その包囲は秦の中華統一戦略の要となる作戦でした。失敗すれば統一事業そのものが頓挫しかねない重大な任務を、楊端和が単独で任されたのです。
この重要な任務を任されたということは、楊端和が始皇帝から絶大な信頼を得ていたことの証拠といえるでしょう。
【独自考察】楊端和が史書から消えた謎
楊端和について最も興味深いのが、趙滅亡後に突然史書から姿を消してしまうことです。この謎について、独自の考察を行ってみましょう。
趙滅亡後の突然の記録途絶
楊端和の最後の記録は、紀元前229年の邯鄲包囲戦です。翌年の紀元前228年に趙が滅亡すると、楊端和の名前は史書から完全に消えてしまいます。
これは非常に不自然なことです。秦の統一事業はその後も続き、燕や楚、斉といった国々との戦いが残っていました。楊端和ほどの実力者であれば、その後の戦いにも参加したはずです。
しかし、史書にはその記録が一切残っていません。一体何が起こったのでしょうか。
可能な消失理由の分析
楊端和が史書から消えた理由として、以下のような可能性が考えられます:
戦死説:邯鄲攻略戦や、その後の戦いで命を落とした可能性があります。古代の戦争では、将軍といえども命の保証はありませんでした。
引退説:趙滅亡という大きな功績を上げた後、自ら引退した可能性もあります。古代中国では、功成り名を遂げた後に隠居する将軍もいました。
左遷説:何らかの理由で始皇帝の信頼を失い、重要でない地方に左遷された可能性もあります。この場合、史書に記録される価値がないと判断されたのかもしれません。
最も可能性が高いのは戦死説ですが、確実な証拠はありません。この謎こそが、楊端和という人物の興味深さを物語っているのです。
蒙驁の後任説の検証
興味深いことに、楊端和が史書に登場するタイミングは、秦の名将・蒙驁が紀元前240年に死去した直後です。まるで蒙驁の後任として抜擢されたかのような印象を受けます。
蒙驁は秦の重鎮として長年活躍した名将でした。その蒙驁の死去により、秦軍に空いた穴を埋めるために楊端和が抜擢された可能性は十分にあります。
この仮説が正しければ、楊端和は蒙驁という大物の後任を務めるだけの実力を持った将軍だったということになります。短期間での目覚ましい活躍も、この観点から見ると納得がいくのです。
山の民の実在性と史実のモデル民族
史実に「山の民」という集団は存在しませんでした。これは完全にキングダムのオリジナル設定です。ただし、当時の中国西部に住んでいた羌族や月氏といった異民族が、山の民のモデルになった可能性があります。楊端和は異民族の王ではなく、秦の正規軍将軍だったのです。
史実に「山の民」集団は存在しない
キングダムファンの皆さんには残念なお知らせですが、史実に「山の民」という特定の集団は存在しませんでした。これは完全にキングダムオリジナルの設定なのです。
キングダム完全オリジナル設定
史実を詳しく調べても、楊端和が率いる「山の民」という集団の記録は一切見つかりません。当時の中国西部には様々な異民族が存在していましたが、「山の民」という名称で呼ばれる特定の集団はなかったのです。
この設定は、原泰久先生の見事な創作によるものです。史実の楊端和という名前と功績を借りながら、「山の民の女王」という魅力的な設定を生み出したのです。
楊端和は秦の正規軍将軍
史実の楊端和は、異民族の王ではなく秦の正規軍将軍でした。彼が指揮していたのは秦の正規軍であり、山岳地帯の異民族軍ではありません。
史記の記録を見ても、楊端和は王翦や桓齮といった他の秦将軍と同様に扱われています。特別に「異民族の将軍」として区別されている記述はないのです。
異民族王ではなく平地の将軍
楊端和は山岳地帯の王ではなく、平地で活動する普通の秦将軍でした。当時の秦は、異民族を味方につけて戦うよりも、正規軍による力押しの戦術を好んでいたからです。
秦の軍事戦略は、圧倒的な兵力と厳格な軍律による正面突破が基本でした。異民族との複雑な同盟関係よりも、確実にコントロールできる正規軍を重視していたのです。
山の民のモデルは羌族と月氏
それでは、キングダムの「山の民」にはモデルがあったのでしょうか。実は、当時の中国西部に住んでいた羌族と月氏が、そのモデルになった可能性があります。
羌族の文化と風習
羌族は、中国西部の山岳地帯に住む遊牧民族でした。彼らは独特の文化と風習を持っており、その一部が「山の民」の設定に反映されている可能性があります。
特に注目すべきは、羌族の「顔を隠す風習」です。史書によると、羌族の祖先とされる無弋爰剣が鼻を削がれた女と結婚し、その女が容貌を恥じて髪で顔を隠していたため、後に羌人がこれを風習としたという記録があります。
この風習こそが、キングダムの山の民が仮面をつける設定の元ネタになった可能性が高いのです。
月氏との関係性
月氏も、紀元前3世紀頃に中央アジアで活動した遊牧民族です。『漢書』西域伝によれば、月氏は羌に近い文化や言語を持っていたとされています。
月氏は最初甘粛地方で農業・牧畜を行い、中国とオアシス諸国の間で中継貿易に利を占めていました。しかし匈奴の冒頓単于に圧迫されて西方に移動し、大月氏と小月氏に分かれることになります。
この月氏の一部が秦の領域内に残存していた可能性があり、それが「山の民」のモデルの一つになったかもしれません。
仮面の元ネタ「顔を隠す風習」
キングダムの山の民といえば、印象的な仮面が特徴的です。この仮面の設定は、羌族の「顔を隠す風習」から着想を得た可能性が高いといえます。
羌族の伝説では、容貌を恥じた女性が髪で顔を隠していたため、それが民族全体の風習になったとされています。原泰久先生は、この史実を現代的にアレンジして「仮面」という設定に変更したのではないでしょうか。
実際に顔を髪で隠している姿を漫画で描くと、読者にとって分かりにくくなってしまいます。そこで「仮面」という分かりやすい視覚的要素に変更したのは、見事な創作判断といえるでしょう。
秦と異民族の実際の関係
史実における秦と異民族の関係は、キングダムで描かれるような協力関係とは大きく異なっていました。
敵対関係が基本
史実では、秦と西方の異民族は基本的に敵対関係にありました。秦は中華統一を目指す過程で、領土拡張のために異民族の土地も征服対象として見ていたからです。
特に羌族や月氏といった民族は、秦の西進政策にとって障害となる存在でした。秦にとって、これらの異民族は「征服すべき対象」であり、「協力すべきパートナー」ではなかったのです。
政治的利害一致時の協力
ただし、政治的な利害が一致した場合には、一時的な協力関係が結ばれることもありました。敵の敵は味方という論理で、共通の敵に対して共闘することがあったのです。
例えば、匈奴という共通の脅威に対しては、秦と一部の異民族が協力することもありました。しかし、これは長期的な同盟関係ではなく、あくまで一時的な利害の一致に過ぎませんでした。
後方の憂いとしての存在
秦にとって異民族は、「後方の憂い」としての存在でした。趙や魏といった強国を攻める際、背後から異民族に攻撃される可能性を常に警戒していたのです。
このため秦は、大規模な対外遠征を行う際には、まず異民族との関係を安定させる必要がありました。完全な協力関係ではないものの、少なくとも敵対行為を控えてもらう程度の合意は必要だったのです。
キングダムのような強固な同盟関係は、残念ながら史実には存在しませんでした。しかし、複雑な政治的駆け引きの中で、時には協力することもあったというのが実際のところです。
楊端和史実と山の民実在の総括|男性将軍の真実まとめ
この記事で明らかになった楊端和史実と山の民実在に関する重要なポイントを、以下にまとめます:
楊端和の史実について
- 楊端和は確実に実在した人物:中国の正史『史記』に明確な記録が残されている
- 楊端和は男性将軍だった:古代中国で女性将軍なら必ず記録されるが、そのような記述は一切ない
- 活動期間はわずか9年間:紀元前238年から229年まで、短期間で重要な戦果を挙げた実力派将軍
- 秦の中華統一に重要な役割:魏の衍氏攻略、趙の鄴攻め、邯鄲包囲など主要作戦に参加
- 史書から突然消失:趙滅亡後に記録が途絶え、その後の消息は不明
山の民の実在性について
- 史実に「山の民」集団は存在しない:キングダム完全オリジナルの創作設定
- 楊端和は異民族王ではない:秦の正規軍将軍として平地で活動していた
- モデルは羌族と月氏:中国西部の異民族がキャラクター設定の参考になった可能性
- 仮面の元ネタは羌族の風習:顔を隠す文化が仮面という設定に発展した可能性
- 秦と異民族は基本的に敵対関係:キングダムのような協力関係は史実にはなかった
キングダムと史実の違い

- 性別の変更:史実の男性将軍が魅力的な女性キャラクターに変更
- 立場の変更:秦の正規軍将軍が異民族の女王に変更
- 活動期間の延長:史実の9年間から長期間の活躍に変更
- 山の民という設定の追加:史実にない集団を創作で追加
この記事を通じて、楊端和の史実と創作の違い、そして山の民の真実について理解を深めていただけたでしょうか。史実を知ることで、キングダムの創作の巧みさがより一層際立って見えてくるはずです。原泰久先生の見事な歴史アレンジを楽しみながら、引き続きキングダムの世界をお楽しみください。
▼キングダム【期間限定無料】